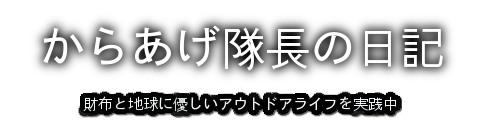こんにちは。からあげです。
昨日は、盆休みの真っ只中というのに、移動してしまって反省している。
早い時間のうちは道路が空いていたが、次第に混み始めた。
田舎の山奥なのに人がたくさんいて落ち着かない。
普段は人気がないところだと思うが、夏休みということでファリミーキャンパーがどっと押し寄せる。
毎日車中泊の生活をしていると、全然キャンプしようなんて思わない。
嵩張って糞重たいオートキャンプ用テントは居住性が良いだけで、設営やメンテナンスの手間、それに保管を考えると大変だなあと思ってしまう。
独りモンには登山用のソロテントが合っている。
そういえば、飯豊山登山を終えてから10日が経ってしまった。
もう随分前のことのように思えてしまう。
あの糞暑くて全身汗でずぶ濡れになって登った記憶は遠い過去になりつつある。
まだ最終日3日目の様子をアップしていないので、台風待ちのこの機会にやってしまうことにする。
飯豊山縦走登山 2泊3日(2016.8.6 3日目最終日) 御西小屋から飯豊山を経てダイグラ尾根より下山
コースタイム
04:20 御西小屋発~05:30 飯豊山~06:45 1830m峰~08:45 休場ノ峰~10:10 桧山沢吊橋~10:35 温身平~11:30 天狗平駐車場着
歩行時間 約7時間10分(休憩時間を含む)
登山ルート

本日は3時10分起床。
快晴で風が少し強め。
気温はそれほど下がらなかったので、夜露は下りなかった。
耳栓をして眠ったので、スマホの目覚ましに気が付かずに寝過ごしてしまう。
小屋の方から聞こえてくる物音でようやく目が覚めた。
2時に起床して小屋の人間が動き出す前に出発しようと目論んでいたが、完全に出遅れてしまった。
取り敢えず寝床を片付けて、旧山小屋の基礎の影に移動した。
寒いので防寒着のフリースを着た。
食事の準備をしていると、トイレ待ちの行列が出来た。
人より早めに出発するようにしているのは、トイレ待ちなどに巻き込まれないためでもある。
小屋の方からは早朝とは思えないくらいの音量で会話するパーティーの声が聞こえてくる。
無理して小屋に泊まらなくて正解だったと思った。
待てども大は催して来なかったので、下山してからすることにした。
山に入ってからは玄米を食べていないので、出るものが出ない。
トイレのタイムロスがなかったので、4時20分に小屋を出発することが出来た。
テントを張らずにシートだけで寝ると時間短縮になって良いと思った。
小屋の前には、宿泊者が食事をしたり、荷物のパッキングをしたりしている登山者の姿が見えた。

小屋から飯豊山(飯豊本山)に向かって緩やかな登り基調となっている。
東の空は明るくなって来ているが、ヘッドランプの明かりなしでは、足元が覚束ない微妙な時間帯。
登山道上には先行者たちの姿がポツポツと見えた。
気が付くと御西岳山頂は通り過ぎてしまっていた。

飯豊山手前の駒形山の登り。
この付近からようやく登りらしい上り坂が現れた。

飯豊山から太陽が覗いた。
山頂はもう目の前。

飯豊山 2,105.2m 日本百名山
飯豊山(いいでさん)は、飯豊山地の標高2,105.1 mの山である。主峰は飯豊本山とも呼ぶ。
飯豊山は、福島県と新潟県そして山形県三県の県境にあるが、南東麓の福島県側から山頂を経て御西岳に至る登山道付近のみが福島県喜多方市になっており、山頂付近は喜多方市である。理由は、明治期に廃藩置県後飯豊山付近が新潟県に編入されたが、飯豊山神社宮とする福島県側の猛烈な反対運動により、参道にあたる登山道および山頂を再び福島県にすることで決着した結果である。そのため、福島県の県境がいびつな結果になっている。

飯豊山山頂付近の県境の様子。
通常は稜線を県市町村の境界としているが、飯豊山だけは特殊となっている。
初めて地図を見た時、なぜこのようになっているのか理解出来なかった。
飯豊山の山頂に着く頃、周囲は一段と明るさを増していた。
雲ひとつない快晴の天気で景色を独り占めした。
本山小屋から登って来た登山者でごった返していると思ったが、誰もいなくて拍子抜けした。

御西小屋方面。
奥には朝日を浴びた大日岳が見える。

左の本山小屋から三国岳方面。
飯豊山に至るメジャーなコースは、川入から三国岳を経て飯豊山を登るコースとなっているようだ。
日帰りだと厳しいので小屋泊まりとなる。
必然的に飯豊山に一番近い本山小屋が一番混むそうだ。
翌日のご来光を拝むためだ。

東の方の空を望む。
朝日を浴びて山々が輝いて見える。

山頂からダイグラ尾根を見下ろす。
今日の本番は、飯豊山からの下りとなる。
靴紐を締めて下りに備える。
よし、そろそろ行くか!

ダイグラ尾根の道に入ると道の状態が一気に悪くなった。
急な下り坂となっていてスリップしないように気をつけて歩いた。
天気は抜群に良いので、雨の心配は全く無い。
時間も余裕があるので、慌てることはないのだ。
マイペースで下りてゆく。
画像の右手前は1,830m峰、左奥は宝珠山。

急坂を下って一息つく。
振り返ると飯豊山の山頂が見えなくなっていた。

1,830m峰
山頂部分が岩となっている。
ここまで来てもまだまだ先は長い。

1,830m峰からの飯豊山の眺め。
どっしりとした山容に圧倒される。

北股岳方面
桧山沢の向こうに見えるのはくさいぐら尾根。
ちょっと変わった名前。

宝珠山の下り。
傾斜は緩くなったが、滑りやすい砂礫帯なので、慌てず慎重に歩く。

千本峰から飯豊山方向を見上げる。
随分と下って来たなあ。
ここからだと遥か遠くに見える。
ダイグラ尾根を下りに選んで正解だった。
ここからさらに下ってゆくと休場ノ峰(やすみばのみね)と呼ばれる見晴らしの良いところに着いた。
ここからあとは下ってゆくのみである。
あとで地図を見て振り返ったら休場ノ峰だと分かった。
ダイグラ尾根で標識があるのは長坂の清水と宝珠の肩のみ、地図を見ながら現在位置を確認しなければならない。

長坂清水
ここから右手の方に水場の方に向かう踏み跡らしきものが見えた。
どこまで降りるのか分からないので、水場の確認はしなかった。
登りの場合は大量に汗をかくので水分補給が欠かせない。
途中の水場を当てにしないで、麓から必要な飲料水を全て担ぎあげる方が安全だろう。

途中の岩尾根
この区間だけ特徴的だった登山道。
ここから下の吊橋まであと僅か。

桧山沢吊橋(ひやまざわつりばし)
下から聞こえる水の音が大きくなってくると吊橋が近い。
突然、樹木が開けて吊橋が見えた。

桧山沢の上流方向

吊橋を渡る。
よく揺れる橋だった。
見た感じそれほど丈夫そうには見えなかったので、一人ずつ渡った方が無難。

河原を歩いて玉川左岸に付けられている登山道の方に進む。
増水すると厄介な場所となりそう。

川沿いの道はところどころ嫌らしい急斜面があった。
日向に出ると汗が噴き出る。
服を着たまま川に飛び込みたくなった。

川沿いの道から林道に出たところ。
ここまで来れば一安心。
温身平(ぬくみだいら)まで一息だ。
温身平までやって来るとお爺さんに会った。
夏休みシーズンになると湯ノ沢ゲート前で案内をしている地元のボランティアの方だった。
二人一組で担当していて、その人はまだ慣れていなくて地理が分からないので、散歩がてら様子を見に来たらしい。
木陰で玄米ご飯の残りを食べていた時にゲートの方からやって来た。
私が仕事をしないで山登りばかりしていると言っても全然引かれなかった。
仕事を引退した爺さんだからかもしれない。
あれこれ話しているうちに疲れがふっ飛んでしまった。

湯ノ沢ゲートを抜けて駐車場まで戻ってきた。
出発前は疎らだった車もそこそこ埋まっている。
ふぅ~2泊3日の飯豊山登山が終わったぞ。
しかし、私の場合は次もあるのだ。
下山したと当時に道具の後片付けが始まる。
さあて山行時の様子はこれでおしまい。
登山の主要装備品と食料

今回はテントを車に残して避難小屋泊まりとした。
テントサイトの情報が少ないので、無難に小泊まりを選択した。
飯豊山の山小屋は非難小屋なので、素泊まりが基本となる。
食料、炊事道具、寝袋など全て自分で用意しなければならない。
75Lザック、ウエストバッグ、ザックカバー、カッパ上下、ポンチョ、銀マット、寝袋(モンベルダウン#3)、防寒着(フリース)、アンダーグラウンドシート(エアライズ#1)、着替え(厚手靴下、綿100%トランクス、ユニクロTシャツ)、長袖シャツ、ウインドブレーカー(フード付き)
着用衣類
登山靴(ゴローS-8)、速乾性厚手靴下、登山用ズボン(モンベルサウスリムパンツ)、綿100%トランクス、ユニクロTシャツ(速乾性)、タオル(首に巻いていた)、帽子
腕時計、スマホ、モバイルバッテリー、USBコード短、デジカメ、デジカメUSBコード、ヘッドランプ、携帯ラジオ、地図、コンパス、現金、トイレットペーパー×2、折りたたみナイフ、熊よけ鈴、爆音ホイッスル
ガスストーブ(ST-310)、カセットボンベ、アルミコッヘル大小、鍋敷き、アルミ風防、チタンフォーク、プラティパス2L×2、ペットボトル500ml×2
食料(2泊3日)

今回の主食は白米とした。
玄米だと長時間水に浸け置きしておかないと美味しく炊けないからだ。
食物繊維を補うために、大麦を少し持って行く。
ご飯1食分は約1.5合。
チャック付き袋に3合ずつ入れた。
昼のご飯は、朝にまとめて炊いてタッパに入れておいた。
お昼になってストーブを出してご飯の用意をするのは時間が掛かるし、休む場所が見つからないかもしれない。
いつでもどこでも食べやすいようにタッパに詰める。
海苔でおにぎりを作ることも考えられるが、海苔は高いし握るのに手間が掛かる。
それに結局袋に入れなければならない。
出来るだけお金を掛けないようにやっているうちに、いつの間にかタッパご飯が定番となった。

白米8食分(計12合)
大麦少々
乾燥わかめ粗塩少々(チャック付き袋に一緒に入れた。味噌汁の具やご飯に載せる。)
袋ラーメン×2
鯖水煮缶×2
魚肉ソーセージ×2
インスタント味噌汁×4
レトルトカレー×3
レトルト中華丼
ライ麦食パン×3枚
カロリーメイトプレーン×6
食事は全部で6回、朝と晩ご飯にはレトルトカレーか中華丼をプラスした。
鯖水煮缶は、1日目と2日目の晩に食べる予定だったが、2日目は食べずに残しておいた。
袋ラーメンは2日目の晩ご飯前に作って食べた。
ライ麦食パンは、初日の丸山尾根の登りでお腹が減るので、追加の行動食として用意した。
カロリーメイトは非常食として全く手を付けないつもりだったが、2日目にお腹が減って途中で3袋も食べてしまった。
白米は二食分の3合は予備食料としておいた。
下山時の残り食料
白米3合、大麦僅か、乾燥わかめ・粗塩僅か、鯖水煮缶、カロリーメイト×3
その他参考事項
何度も書いているように飯豊山の山小屋は避難小屋で素泊まりが基本。
全ての道具や食料は全て自分で持って行かなければならない。
シーズン中、管理人さんが常駐している小屋は飲料水の心配はない。
ただ場所によっては水不足になる小屋があると思うので、事前に情報収集しておく方が良い。
早めの到着でも避難小屋という性質上、優先権は発生しない。
後から登山者が来れば拒むことなく宿泊させる。
避難小屋なので、事前予約は必要ないが、大人数のパーティーの場合は予約しておいた方が管理人さんに喜ばれる。
夕方になって大挙して来られても困ってしまう。
管理人さんからの情報によると、食事の提供は本山小屋、御西小屋、切合小屋のみ行っている。
食事はアルファー米、レトルトご飯にレトルトカレーのみ。
数には限りがあって在庫がなくなれば終了となる。
どうしても小屋で食料を入手したい場合は事前予約が必要。
団体のツアー客に需要があるのだとか。
参考までに御西小屋の飲食物の料金を書いておくことにしよう。
御西小屋飲食物料金表
コカ・コーラ 500円
アクエリアス 500円
CCレモン 500円
ビール(350ml) 800円
日本酒(菊水) 800円
焼酎 500円
アルファー米 500円
(五目ごはんとわかめご飯あり)
レトルトご飯 600円
レトルトカレー 600円
レトルト中華丼 600円加熱、湯が必要の場合は別途追加料金が必要。
小屋の周囲にはたいていテントを張れる場所がある。
小屋は混むので、混雑するのが嫌であればテントを持って行った方が良い。
管理人さんと話した感触では、空いていて小屋がガラガラの時は出来るだけ小屋に泊まって欲しい、混んでいる時にはテント泊の方が助かるという感じだった。
テントは植生にダメージを与えるので、飯豊山では出来るだけ自粛して欲しいという雰囲気。
かと言って超満員の小屋では疲れも取れないので、ツエルトを持って行って状況によって小屋かテントを選ぶ方が良いだろう。
私は御西小屋の混雑のぶりに嫌気がさして、たまたまザックの底に入っていたシートを敷いてそのまま外で寝てしまった。
シュラフカバーになるポンチョを持っていたのも大きい。
朝日連峰の方は全面テント泊禁止となっているので、小屋は混雑すると思われる。
私は混んだ小屋に泊まるのは嫌なので、夏山シーズンはトレランで日帰りで登ろうと思う。
最後に標高が低くて暑いので、夏場は暑さ対策をきちんとしておいた方がいい。
樹林帯の登りは風が吹かないので猛烈に暑い。
汗をやたらかくので、飲料水も多くいる。
こまめに水分補給出来るようにプラティパスにハイドレーションを付けるのが良いと思った。
飯豊山の情報ならココ。
飯豊山の登山に関するあらゆる情報が手に入る。
小屋の管理人さんや地元の方が実際に歩いて集めた登山道の情報がアップされている。
私は登山前にここを読んで勉強した。
このHPを熟読すればたいていの情報は集まる。
もしなければ、HPの掲示板で尋ねてみるか、実際に小屋に問い合わせてみれば良いだろう。